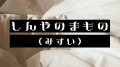新たにカルデアへ顕現したサーヴァントとは、親交を深めるために二人きりで食事を取ることにしている。最近ではすっかり絆が深まってから行うことが多くなってしまったが、それでも細々と続けている。
普段は書類や機材を乗せる台車だが、食事会の度にサービスワゴンとして活躍することになる。食堂で用意してもらった食事と、特別な日だからと他のサーヴァントが用意してくれたおやつを乗せ、マイルームへ意気揚々と向かっていく。
「以蔵さん、お待たせしました!」
がらりと自室の扉を開けば、つい先日――帝都で縁があり、カルデアでも顕現することが出来たアサシン、人斬り以蔵と名高い岡田以蔵が既に寛いでいた。
「おお、もう始めちゅうがよ」
以蔵さんは盃をわたしに掲げ、一気に飲み干した。酒瓶の数は少なくない。ドレイクか、それとも酒呑童子か。いや、この際どちらでも良い。食事はつまみになりそうである。
「待っていてくれたら良かったのに……」
「ここじゃ酒は貴重やき、我慢できんがじゃ」
すまんすまんと笑う顔がへらりと穏やかであったから、すべてを許してしまった。絆はすでに他のサーヴァントと変わらないくらい深まった、と思う。
「マスターは酒はいかんのか」
「うん、わたしはお茶だよ」
「ほうかほうか、どれ、煎れちゅうから座れ」
顕現したサーヴァントには現代の知識が一通り与えられる。ポットを使ってお茶を入れるくらい簡単らしい。出会ったばかりはなれなれしくするなと警戒されてばかりだったことを思えば、お茶を用意してくれるというのに内心涙が出る思いだった。
小さなテーブルを食事で一杯にして、お茶の入ったマグカップを持ち合えげる。なみなみ酒で満たされた杯がすいと持ち上げられたのを境に、乾杯をした。
話はとても弾んだ。例えば、帝都で会った以蔵さんの話。成長するサーヴァントとして、カルデアのセイバーやアサシン、とにかくあらゆる技術を持つ英霊たちの技術は盗みがいがあるという話。今までに行った特異点での冒険を、本当に、たくさん話した。いつの間にやらたくさんの食事はなくなっていたし、おやつだってすっかり消えた。酒のつまみは塩があれば良い、という以蔵さんはわたしの話を楽しげに聞いていた。
「まっこと長い旅をしちゅうが、おまんは逃げんかったんじゃの」
それは、生きたかったからだ。わたしが生きたいという願いに、世界の全てを付き合わせてしまったような居心地の悪さがほんの少しあるが、この場で伝えることはないだろう。すっかり冷たくなったマグカップを握り、曖昧に笑った。
「……のう、マスター? こじゃんと頑張ったおまんにご褒美やるき」
「ご褒美?」
「食堂でなあ、みんなあが取りあっちょったんじゃが……わしがマスターと夕餉じゃ言うたら譲ってくれたんじゃ」
以蔵さんはどこに隠していたのか、小さな白い箱を取り出す。わざわざ化粧箱を用意してあるあたり、エミヤが気を遣って用意したものかもしれない。あの先輩は気が利きすぎるところがある。
「開けるね」
箱を受け取り、開ける。そこにはちいさなガラス瓶に入ったゼリーがふたつ並んでいた。薄い緑がかったそれは、空気に触れてふるりと震えている。
「おまんの好いちゅうやつか?」
「うん、でも二つ入ってるから、一緒に食べよう」
「ほうか、そいたら食う」
ひとつを取り出し、以蔵さんに渡す。スプーンは、と探すより先、以蔵さんは食事に使っていた箸でぺろりと食べてしまった。喉に詰まらなくてよかった。 英霊がゼリーを喉に詰まらせて座に帰るなど、冗談や与太の類いだ。
化粧箱の外側にテープで留められていたスプーンを見つけ、わたしはそうっとゼリーを掬う。
「ん~……」
ふるふると震えるそれを口の中に放り込めば、どこかなつかしいメロンの香りが鼻の奥をくすぐる。喉の奥へ落ちていく感触に、思わず頬が緩んだ。
「うまか?」
「おいしい~……あ、以蔵さん? これくれたのって、赤い服で…えっと、白い髪のお兄さんだった?」
お礼をしなくちゃいけない。新たな英霊を歓迎するためにわざわざデザートを作ってくれるなんて、気が利くにもほどがある。貴重な材料を使わせたのであれば何か差し入れなくては。
「いや? なんらあ……あの、角が生えてて、着物引っかけてる黒い方の鬼よ」
「……酒呑童子?」
「そう、そう。みんなあいいやつら」
もう一口を食べようとして、一度スプーンを置いた。以蔵さんの口が回っていない。なんなら、目線もぽやぽやとどこか遠くを見つめている。
「ね、以蔵さん? これ、何のゼリーって言ってた?」
「ああ……なんちゃあいうてたかな、さけ…?」
酒呑童子、酒とくれば彼女の宝具である。真名解放があれば魔力を通じて自分にもわかるから、恐らくそのまま酒として使われたのだろう。もしかしたら、サーヴァントである以蔵さんには何か影響があったのかもしれない。
わたしに魔力は殆どない。マスターとして、ほんの少しの治癒を行えるくらいだ。酒気が効き過ぎたのかもしれない、英霊は意図的にアルコールに酔わないことも出来るはずだが、それに至らないほど酔っているということだろう。
「おまんが飲めんいうからなあ、こういうのならええんじゃいかと……」
「以蔵さんは悪人ですねえ……」
随分かわいらしい範囲ではあるが。椅子にぐったりと寄りかかる以蔵さんの頬を両手で挟み、微かな魔力を送る。肌と肌を介していれば、多少ましだろう。
「……えいなあ、おまんの手はぬくい」
とろとろと眠たげな目をした以蔵さんは、頬に当てたわたしの手をしっかりと掴む。硬い手のひらが、わたしの肌を撫でていく。
「ちくとそんまま……」
金の目が瞼で隠れる。間を置かず、寝息が聞こえてきた。
天誅の名人と呼ばれた男は、わたしの手を柔く握ったまま穏やかに眠ってしまった。警戒などなく、まるで子供のように。
「……悪いひとだなあ」
せめてこの手の力が緩まるまでこうしていよう。温かな手に触れることは、わたしもまた嬉しいのだ。穏やかな寝顔を見ながら、この後どうやってベッドに叩き込むかを考えることにした。