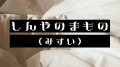連れて行きたい場所があるから、と言ったのは嘘ではなかった。
キール山地を越えた灰の国には黄金色の草原があった。黄金色の草原と言えば幻想的な景色のようだが、端的に言えば麦畑である。
ただの麦畑だけれど、山の麓を埋め尽くすような黄金が延々と続いているのはため息が出るほど綺麗なのだ。放浪の最中に見たそれが忘れられず、何より、綺麗だと思ったからウェンドリンにも見せたかった。
「何もないわね、キレハ」
ウェンドリンはくすくすと笑っている。私はただ、目の前の景色に立ち尽くしている。そこには視界を埋め尽くすほどの黄金色があるはずだったのだが、……何もない。
足下に刈り取られた麦の穂が落ちていた。拾いあげて、ウェンドリンに渡す。麦の穂を指先で遊ばせ、丸々と膨れたその実が揺れる。麦が太れば収穫する。当たり前のことだけれど、そんなことすっかり忘れていた。
「……収穫祭、間に合わなかったわ……」
まさか、収穫後の麦畑を見せることになるとは思わなかった。これならきっと、彼女の故郷であるホルムで見ることもあっただろう。
ホルムの街。ネス公国と西シーウァ王国の国境にほど近い、ウェンドリンの故郷。過ぎ去る時の中にその姿を消してしまった街。彼女に残された呪いと祝福の一部が、彼女から奪っていったものの一つだ。長き時が過ぎ去り、彼女を記憶する全ての人々は死に絶えてしまった。その記録を持つ街もまた、姿を消した。
その街を離れて、一ヶ月が経った。
英雄たちを祀るという祭事を見ながら、私たちは今日のようにただ立ち尽くしていた。
帰ってこなかった英雄たちが帰ってきてしまったと知ったら、この祭りはどうなるのだろう。おかえり、と出迎えてくれるのだろうか。誰も私たちのことを、知らないのに。
かつてここにあったホルムという街はなくなり、今は全く別の街が存在している。長い時が過ぎて、どうやら世界は大きく変わってしまったようだった。
ホルム領主の娘として生きてきたウェンドリンの心境は、私にはわからない。寂しいのだろうか。それとも、背負うべきであった領主の娘としての責務から逃れ、安堵しているのだろうか。
上流から白い花が流れてくる。大河の緩やかな流れに巻かれてくるくると回りながら。何故か、日が昇って沈み、月が浮かんでは消えてゆく、アーガデウムで見た永遠のような景色を思い出した。
「一緒に行かない?」
私の声は、掠れてしまっていた。ウェンドリンは目を丸くして、私の目をじっと見つめる。私は、約束を覚えているか聞けば良かったとほんの少し後悔していた。
――狭い場所に囚われすぎて、余計なことを背負い込んでいるように見えるんだもの。
そう言った私の言葉は、どこまでがウェンドリンに向けた言葉だっただろう。頭の隅で、私も囚われているのかもしれないと考えていたからこそ出た言葉のような気がしていた。
あてのない旅。自分の影を探すという目的。故郷を離れてなお私を縛る一族の血を、ほんの少し重荷に感じていたせいなのかもしれない。
「あなたに見て欲しいものがたくさんあるの、私」
「……いつか言っていた、キレハの故郷?」
「それだけじゃないわ」
行き先も目的も決まっていない旅路の中で私を癒やしてくれたのは、美しい景色だった。その土地のもつ表情と言い換えても良いかもしれない。深い森に差す木漏れ日、あまりにも透明すぎる湖、黄金色の平原。綺麗だと思うそれを、ウェンドリンに見せたかった。
世界はホルムだけではないもの、と言いかけてやめた。
「……それも、いいかもしれない」
ウェンドリンは流れてきた花を見て、ぽつりと呟いた。
「私は、ホルムしか知らなかったから」
流れてくる花と花が重なって、川の中州でぴたりと止まった。ウェンドリンが手を伸ばし、花は再び流れていく。
「大河がどこまで続くかも、知らない」
知識としては知っているけれど、と苦笑する姿を見て、私はほっとしていた。共に行くことができるのだと思うと、嬉しかった。
「キレハがいれば、ご飯も安心だし」
「……それだけ?」
「大事でしょう? ご飯は」
ぐう、とほとんど同時に腹が鳴った。それでようやく、お腹が空いていることに気がついた。たとえ故郷が滅んでも、生きているからお腹が空く。
二人でパンを焼きながら、どんな景色が見たいかと話をした。ウェンドリンは知識だけは持っていて、今まで足を運んだことがない場所に強く興味を示した。ホルム領主の娘であることから離れた彼女は、驚くほど貪欲だった。
「キレハの故郷にいくなら、どうすればいいのかしら」
「……ずっと北にいけばいつかは辿り着けると思う」
今、故郷はどうなっているのだろう。かつてのホルムでたき火を囲みながら考える。それを確かめにいくのも、いいだろう。
「その間に綺麗なものはあるかしら」
「ここからなら……キール山の麓にある黄金草原?」
地図が機能するかはわからないけれど、二人で地図を広げて道を考える。目的地のある旅と言うのは、こういう風にするのだと初めて知った。
そうやって、黄金色の草原を目指して来た結果が、これである。既に収穫を終え、ただの畑になってしまった畑は、確かに人の生活に基づくものだけれども、私が求めたそれではない。ただ、ウェンドリンは人が生活している様子が変わっていないことにほっとしているようだった。
「私よりキレハの方がずっとがっかりしてる」
麦の穂をくるくると指先で遊ばせながら、ウェンドリンが笑っている。笑ってくれるならまだ、ましだろうか。
「……そうよね、麦だもの……収穫するわよね……小麦にしなきゃパンも作れないし、考えればわかったはずなのに……うっかりしてた」
「キレハが楽しそうだったから、私はそれでもいいけど」
ウェンドリンは麦の穂で私の頬をくすぐる。その表情はとても優しいのだけれど、赤い瞳の奥に寂しさの気配を感じている。
ウェンドリンは旅の中で、与えられた呪いと祝福の話を私に教えてくれた。永遠の命を与えられた、と言うことを。
それから、ちらりちらりと、瞳の奥に何かが過ぎるようになった。実際に見えるわけではなく、その気配があることを感じる、という程度だけれど。
今も、それがある。ウェンドリンの声音から、隣にいるのではなくもっと俯瞰的な存在として私を見ている。距離を感じるのだ。
「ウェンドリンは?」
「私も楽しかったよ、見られなかったのは残念だけど」
笑う横顔に、仕方ないと事態を飲み込むわかりの良さを見た。そうではない。そういう顔を、させたいのではない。私は、私がウェンドリンとしたいことは。
「来年、見に来ましょうね」
私は、麦を持つウェンドリンの手をしっかりと握りしめていた。はらりと麦の穂が落ちる。ウェンドリンは目をぱちくりさせていた。手を握ったことを驚かれたのかと、そろそろとその手を離す。
「来年?」
「また、麦を植えるでしょ? そうしたらまた……」
「……そっか、来年、そう……そうだね!」
ウェンドリンは何度も頷きながら、私の手をしっかりと握った。頬が僅かに蒸気している。
「……キレハは真面目だから、約束を果たしたら故郷に帰ってしまうのかなと思っていたの」
ウェンドリンの瞳の奥に過ぎる寂しさの原因は、恐らくそれである。私の故郷と、美しい景色を見せて、それで約束を果たしてお別れになると考えていたのなら、彼女の胸中に迫る寂しさの波は余程大きかっただろう。
私は、素直に驚いていた。今まで誰とも旅を共にすることはなかった。だから、別れも知らない。そうだ、いずれ別れるということがあるのだ。ようやく何に囚われることもなく、一人の人間として生きていけると言うのなら、それが尽きるまで共にいたいと考えてしまっていた。
「馬鹿ね、ウェンドリン」
「……そうね、本当に」
いつまでとは、言わない。言えなかった。思いつかなかった、というのもある。
「来年、かあ」
「本当に……綺麗だから」
記憶にある黄金色の草原は、風が吹くと一斉に波が広がっている。山から下りてくる風は冷たく、強い。体ごと持って行かれそうになりながら、髪を風に巻き上げられながら、それでもその黄金色の波を眺めていたくなる。
その黄金色の中に、ウェンドリンが立っていたら、綺麗だろうと思った。一人だけ、黄金色ではなく真っ白な髪を風に揺らすウェンドリンが立っているのは、とても尊いもののような気がする。もちろん、その隣に私もいたい。
「それまでどうしよう?」
「他の場所にも行ってみようよ」
「キレハはそんなに行きたいところがあるの?」
行きたいところは、さして思いつかない。
「どこでも……ウェンドリンが知らない場所、たくさん見て欲しいと思っているから」
また、ウェンドリンの瞳の奥に寂しさが過ぎる。
「……そうだね、私も、全部覚えていたいと思う」
その寂しさを、少しでも埋めてやりたいと思う。できるだけ、長い時間をかけて。それがほんの少しでも。
「ウェンドリンは、難しく考えすぎなのよ」
繋いだ手の温もりも、今すぐに消えることはない。明日だって側にいて、黄金色の草原を待つ間に何をするか考えている。考え続けている。
「特別なことなんかじゃないでしょう?」
キール山から吹く風が、私とウェンドリンの間を吹き抜けて行く。冷たい、北の国からくる風だ。ぶるりと体が震える。ウェンドリンがそっと私の手を両手で包んだ。剣で豆のできた、けれどやわらかな手だ。
「もう少し、くっついてよう」
「……仕方ないわね、本当に」
風はもう止んでいる。それでも、ウェンドリンの手が離れることはなかった。